小児に見られる歯肉炎は、言わば歯周病の前段階のようなものであり、歯茎が腫れたり、赤みが出たりといった症状を伴います。
症状は軽度であることが多く、しっかりケアをすれば治まってきますが、こちらにはいくつかの種類があります。
今回は、小児における歯肉炎の主な種類と特徴について解説します。
萌出性歯肉炎
小児における歯肉炎の種類としては、まず萌出性歯肉炎が挙げられます。
こちらは、歯が生えてくるのに伴って起こる歯肉炎で、生え始めた乳歯や、第一大臼歯、第二大臼歯など、新しく生えてくる歯にしばしば見られます。
歯が生えてくるときには、その周囲の歯茎を押しのけるように生えてきますが、そのために歯茎の形が変わり、食べカスやプラークがつきやすくなるのが原因で起こるのが、こちらの歯肉炎です。
また、萌出性歯肉炎には、歯茎の腫れに加え、むず痒い、歯磨きのときに痛いといった症状があり、歯が生え終わってもなかなか治まらない場合には、歯科クリニックの受診が必要になります。
萌出性歯肉炎を放置するとどうなる?
萌出性歯肉炎を放置した場合、炎症が歯茎の奥にまで広がり、より重度の歯周炎へと進行する可能性があります。
歯周炎は歯を支える骨を破壊し、最終的には歯が抜け落ちる原因にもなります。
また萌出性歯肉炎をそのままにしていると、永久歯の萌出や歯並びに悪影響を及ぼすこともあります。
さらに子どもの頃に発症した歯肉炎を放置すると、大人になってからの慢性歯周炎に移行しやすくなり、永久歯の早期喪失につながるおそれもあります。
つまり、子どもの歯の将来にも良くない影響を与えるということです。
不潔性歯肉炎
小児における歯肉炎の主な種類としては、不潔性歯肉炎も挙げられます。
こちらは、歯磨きが不十分でプラークが溜まり、歯茎に炎症が起こることで発症するもので、小児の歯肉炎では、もっとも多いタイプです。
具体的には、歯が十分に磨けていないことで、口内の細菌が増加し、歯茎に傷がつくられた際に、そこから感染するケースがよく見られます。
小児の場合、歯磨きの力加減がわからず、歯茎を傷つけることもあり、そこから発症することもあるため、注意しなければいけません。
ちなみに、不潔性歯肉炎は、丁寧に歯磨きをしてプラークを取り除いたり、歯石を除去したりすることで治るケースがほとんどです。
不潔性歯肉炎を放置するリスク
不潔性歯肉炎も、萌出性歯肉炎と同じように放置することで、重い歯周炎へと段階を移します。
歯周炎になると歯茎だけでなく、歯を支える歯槽骨にも炎症が及び、骨が溶けるため注意しなければいけません。
また骨が溶けると当然歯が抜け落ちるリスクは高まりますし、心臓病など全身疾患にも影響を与える可能性があります。
もちろん、永久歯の生え方や顎の発育にも影響を与える可能性があります。
思春期性歯肉炎
思春期性歯肉炎も、小児に見られる歯肉炎の1つです。
こちらは、主に小学校高学年~中学生(10~15歳頃)に見られる歯肉炎です。
思春期の間は、プロゲステロンやエストロゲンといったホルモンが増え続け、歯肉への血流量が増えます。
その結果、新陳代謝が活発になり、プラークや食物残渣といった刺激物への反応が高まり、歯茎が腫れて破れやすくなります。
そのため、通常の歯ブラシに加え、デンタルフロスを使用するなど、家庭でのデンタルケアがとても重要です。
思春期性歯肉炎を放置するとどうなる?
思春期性歯肉炎は、名前の通り思春期の発症する歯肉炎です。
そのため、放置することのリスクとしては、心理的な影響が大きくなることが挙げられます。
口元の見た目や口臭といった問題は、思春期の子どもにとって自信を失ったり、人とのコミュニケーションをためらったりする原因になります。
また歯肉炎の影響により、なかなかコミュニケーションができないまま育ってしまうと、大人になってからもそれを引きずってしまうことが考えられます。
コミュニケーション不足は、交友関係の構築を阻害したり、仕事においては連携不足によるミスや生産性の低下を引き起こしたりすることもあります。
子どもの歯肉炎を予防するには?
子どもの歯肉炎を予防するために共通して言えることは、やはり毎日の丁寧なブラッシングを徹底することです。
ブラッシングの際は、歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目に当て、小刻みに優しく磨きます。
歯と歯の間については、デンタルフロスや歯間ブラシで清掃することをおすすめします。
子どもが自分で磨けるようになったとしても、小学校中学年くらいまでは親御さんの仕上げ磨きが必要です。
また定期的な検診も、子どもの歯肉炎を予防するためには欠かせません。
3~6ヶ月を目安に、歯科クリニックで検診を受けましょう。
ちなみに歯科検診では、口内にトラブルが発生していないか確認するだけでなく、ブラッシング指導や歯石除去などのクリーニング設けることができます。
もちろん、食生活や噛み方、口呼吸といった生活習慣を見直すことも大切です。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・小児に見られる歯肉炎は、歯周病の前段階のようなもの
・萌出性歯肉炎は、歯が生えてくるのに伴って起こる歯肉炎
・不潔性歯肉炎は小児にもっとも多く、プラークが溜まり、歯茎に炎症が起こることで発症する
・思春期性歯肉炎は、ホルモンの影響で歯茎が腫れ、破れやすくなるという症状
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
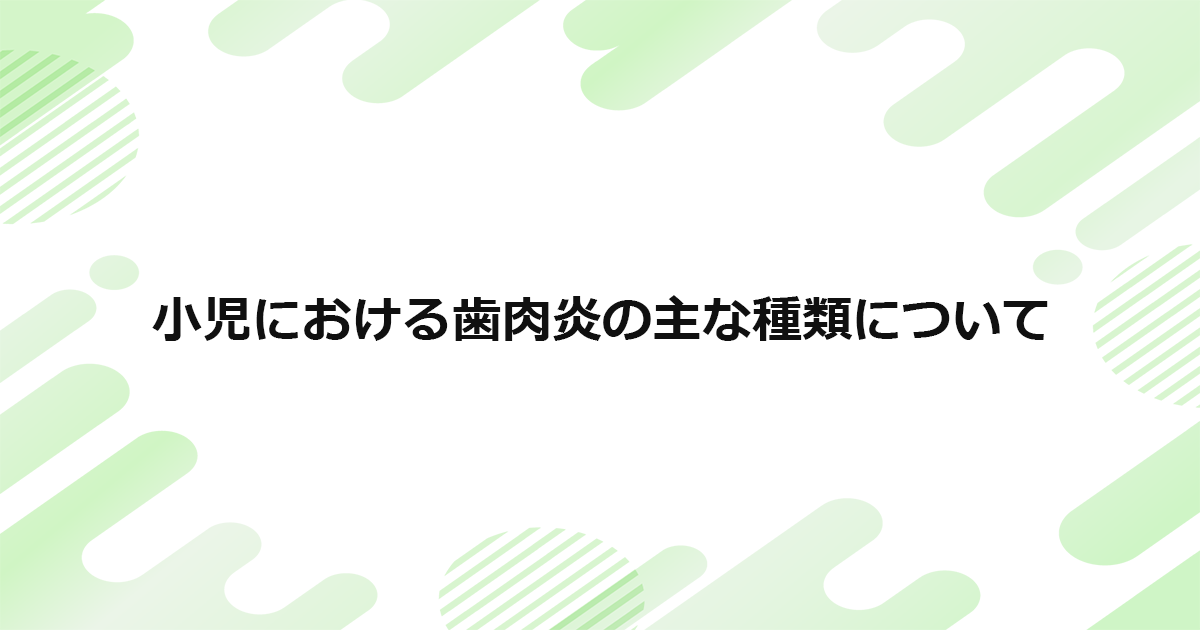

患者様のことを最優先に考えた、オーダーメイドの治療プログラムで対応させて頂きます。