口内炎は、軽度のものから重度のものまで存在し、場合によっては歯科クリニックで口腔外科治療を受けなければいけないこともあります。
また、一口に口内炎といってもその種類はさまざまであり、種類によって原因や特徴なども異なります。
今回は、主な口内炎の種類について解説したいと思います。
アフタ性口内炎
アフタ性口内炎は、口の中の粘膜に形成される、境界線がハッキリとした小さい腫瘍(アフタ)が多発し、周辺に粘膜炎を伴っている症状であり、もっとも一般的な口内炎です。
頬の内側や舌、唇の裏や歯茎など、さまざまな場所に現れるもので、痛みや食事をしたときにしみるなどの症状を伴います。
また、こちらの大きな原因は免疫力の低下であり、根本的な対策が難しいため、発症してから治療することになります。
基本的には、口内炎自体の痛みを和らげるために、ステロイドの塗り薬や貼り薬などが処方されます。
カタル性口内炎
カタル性口内炎は、口内を誤って噛んでしまったり、火傷や入れ歯の不具合など、物理的な刺激や傷があったりした場合に発生する口内炎です。
外的な刺激によって粘膜が傷つくことで、赤く腫れたり、ただれたり、潰瘍ができたりします。
また、このような口内炎は傷が回復すれば治るため、基本的には塗り薬を使って治療します。
入れ歯の不具合が原因である場合は、口内で擦れないよう、入れ歯の形状や位置などを調整します。
ウイルス性口内炎
ウイルス性口内炎には、主にヘルペス性口内炎、カンジダ性口内炎の2種類があります。
ヘルペス性口内炎は、単純性ヘルペスウイルスに感染することで発症するもので、白っぽい水ぶくれのような症状が出ます。
カンジダ性口内炎は、カビの一種であるカンジダ菌が原因の口内炎で、体力が落ち、抵抗力がなくなったときに引き起こしやすいです。
症状としては、口や喉の粘膜、歯茎の粘膜に、白っぽいカビのようなものがつき、粘膜がピリピリする、チクチクするなどの症状が出ます。
また、これらのウイルス性口内炎は、いずれも薬物療法を中心に対処し、痛みのために食事が摂れない場合は鎮痛剤も処方されます。
ニコチン性口内炎
ニコチン性口内炎は、慢性的な喫煙習慣が原因で起こる口内炎です。
具体的には、タバコに含まれるニコチンが口内の血流を悪くすることで、粘膜の障害を引き起こします。
またタバコの呼気による熱で口内が乾燥し、細菌が繁殖しやすくなることも原因の一つです。
さらに、タバコに含まれる化学物質が粘膜を刺激し、口内炎を形成させることもあります。
発症部位としては、喫煙のとき煙が触れやすい上顎の粘膜が多く、粘膜が赤くなった後は白く厚く変化し、白い斑点状になることがあります。
痛みは少なく、食べ物がしみる程度のケースが多いです。
ちなみに長期間の喫煙により、ニコチン性口内炎が口蓋ニコチン性白色角化症と呼ばれる状態になることもあります。
こちらは口腔がんの前がん病変であり、非常に危険です。
口内炎に使用できる市販薬について
口内炎の治療は歯科クリニックで行うことができますが、市販薬も効果を発揮することがあります。
口内炎の市販薬は、大きく2種類に分けられます。
1つは、ステロイド配合薬などの塗り薬、もう1つは抗炎症成分配合薬などの内服薬です。
ステロイド配合薬は、炎症を抑えるステロイドを含むもので、優れた密着力で患部を保護し、症状を早く抑えたい場合に効果的です。
また抗炎症成分配合薬については、トラネキサム酸やグリチルリチン酸ジカリウムといった炎症を鎮める成分が配合されたものがあります。
ちなみに、うがい薬も口内炎に効果を発揮することがあります。
例えばポビドンヨードを含むうがい薬は、さまざまな細菌やウイルス、真菌に有効であり、口内炎の症状にも効果があります。
ただし口内炎の症状が2週間以上続く場合、痛みが極めて強い場合などは、市販薬で対応せずすぐに歯科クリニックを受診すべきです。
口内炎を予防するための基本的な対策
口内炎のリスクを少しでも下げるには、生活習慣の改善と口腔ケアの習慣が大切です。
食事ではビタミンB群やビタミンCを積極的に摂取し、粘膜の健康を保ちましょう。
また疲労やストレスは免疫力を低下させ、口内炎の原因となるため、質の良い睡眠を十分に取ることも大切です。
さらに、ブラッシングやうがいを習慣づけ、口内の細菌やウイルスを減らすことも重要です。
ブラッシングの際は、歯茎や粘膜を傷つけないよう、力を入れすぎずに優しく磨くことを意識します。
その他口内の乾燥を防ぐためこまめに水分補給を行ったり、適度な運動やリラックスできる時間をつくったりすることも、口内炎予防につながります。
ちなみに、辛いものや熱いものなど、粘膜への刺激が強いものはなるべく避けるのが無難です。
入れ歯や矯正器具を使用している方は、定期的に洗浄・清掃し、清潔に保ちましょう。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・アフタ性口内炎は、小さい腫瘍が多発するもっとも一般的な口内炎
・口内を噛むなど、物理的な外傷により、カタル性口内炎を発症することがある
・ヘルペス性口内炎は、単純性ヘルペスウイルスに感染することで発症する
・カンジダ性口内炎は、カビの一種であるカンジダ菌が原因の口内炎
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
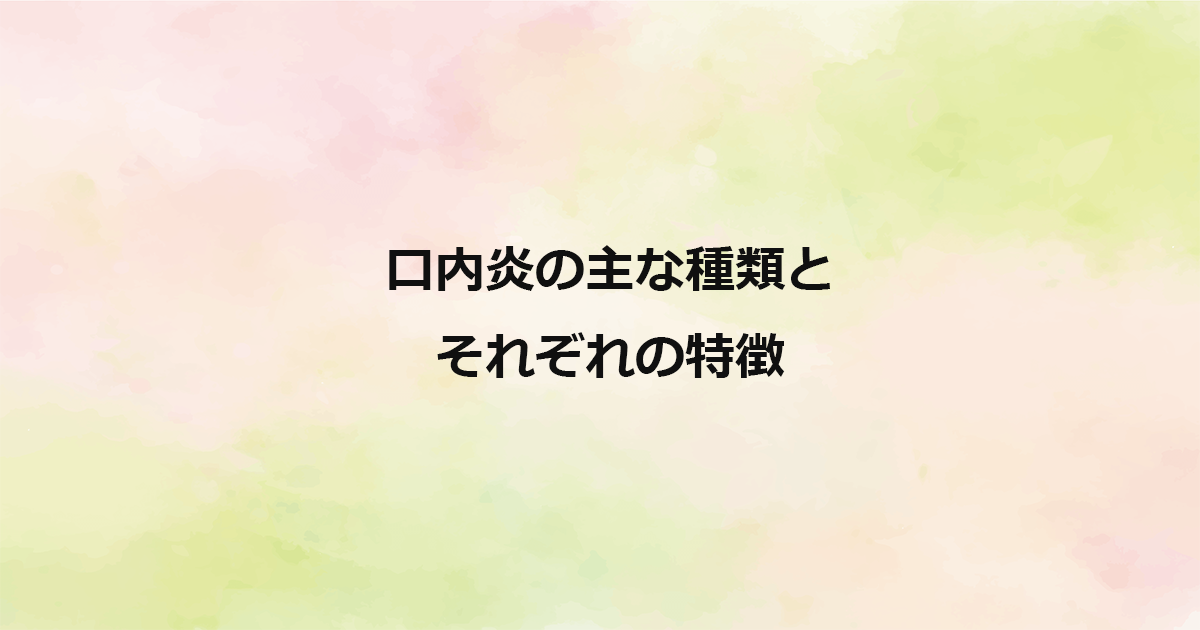

患者様のことを最優先に考えた、オーダーメイドの治療プログラムで対応させて頂きます。