小児の中には、無意識のうちに特定の行動を行っている子もいます。
こちらは大人にも言えることですが、小児の場合、このような癖が歯や顎に良くない影響を与えることもあるため、注意しなければいけません。
ここからは、小児における口周りの悪い癖とその影響について解説したいと思います。
舌癖
小児における口周りの悪い癖としては、まず舌癖が挙げられます。
こちらは、舌で歯を押したり、触ったり、歯と歯の間に舌を押し付けたりする癖のことであり、食べ物を飲み込むたびに行っているケースも見られます。
一見、何でもないような癖ですが、こちらは歯が傾き、出っ歯になることや、舌が後方に下がり、受け口になったりする原因になりかねません。
また、上下の前歯で舌を噛んだり、隙間に押し付けたりすることで、前歯が閉じない開咬の状態になることも考えられます。
ちなみに、舌癖から口呼吸が引き起こされることにより、ウイルスや細菌が入りやすくなる可能性もあります。
唇を噛む
小児における口周りの悪い癖としては、唇を噛むことも挙げられます。
こちらは、上下いずれかの唇を無意識に噛んでしまうというものであり、噛み方によっては舌癖同様に出っ歯になったり、受け口につながったりするものです。
どちらかというと、下唇を噛んでいるケースが多く、親御さんには、見かけたタイミングで適宜やめさせることをおすすめします。
硬いものを噛む
小児における口周りの悪い癖としては、硬いものを噛むということも挙げられます。
もっともよく見られるケースは、自身の爪を噛むというケースです。
爪を噛む場合、小児は前歯で爪を噛み、指を細かく前に引っ張るという行動を取りがちですが、こちらの影響で前歯が前方に引かれる時間が長くなり、出っ歯への影響が懸念されるようになります。
そのため、指しゃぶりをしていない小児でも、こちらの癖がある場合は注意が必要です。
また、爪以外でいうと、鉛筆などの表面を噛むというケースも見られます。
このような硬いものを日常的に噛むと、歯や歯茎に負担がかかり、正常は発育を妨げたり、歯並びを乱したりしてしまうおそれがあります。
口呼吸
舌癖の項目でも少し触れましたが、口呼吸も小児における口周りの悪い癖です。
こちらは、本来鼻を通して行うべき呼吸が口で行われている状態であり、アレルギー性鼻炎や扁桃腺の肥大などさまざまな原因で発生します。
口呼吸が続くと、顎の発達が阻害されて顔が長くなったり、呼吸器系の感染症にかかりやすくなったりします。
また口呼吸が慢性化すると、舌の位置が低くなることが多く、歯並びの乱れを引き起こします。
ちなみに口呼吸によって引き起こされる不正咬合には、開咬や過蓋咬合、交叉咬合や上下顎前突などが挙げられます。
指しゃぶり
小児における口周りの悪い癖には、指しゃぶりも挙げられます。
指しゃぶりは多くの乳児に見られる癖であり、子どもの成長において重要な役割を果たします。
一般的には、3歳頃までに自然とやめるケースが多いです。
しかし、稀に4歳を過ぎても指しゃぶりを続ける子がいて、こうなると歯並びに良くない影響を与えることがあります。
指しゃぶりを続けると、指が上下の歯に挟まれた状態が継続します。
これにより、歯が押されて前歯の位置がずれ、外側に広がります。
結果的に上下の前歯に隙間ができる開咬、歯と歯の隙間が生じる空隙歯列、上顎前突などにつながります。
よく噛まない
食事の際によく噛まないことも、小児における口周りの悪い癖だと言えます。
現代は昔に比べてやわらかい食べ物が多く、食事の際に咀嚼する回数は減ってきています。
しかし、よく噛むということは脳の活性化や肥満防止、味覚の発達や唾液の分泌による虫歯・歯周病の予防などにつながります。
また歯並びへの影響も大きく、噛むことで唇や舌、顎や顔周りの筋肉をしっかり使って発達させることで、歯並びの悪化を予防できます。
ちなみに食事の際、飲み込むタイミングは食べ物がおかゆ状になってからです。
大体一口で30回ほど噛むのを目安にしましょう。
姿勢が悪い
小児の姿勢が悪いと、歯並びなどに悪影響を及ぼすことがあります。
例えば猫背の場合、背中が曲がって頭や顎が前に出ます。
このような状態は口を開ける筋肉が優位に働くため、口が開いて口元の筋力バランスが崩れたり、口呼吸につながったりしやすくなります。
また本来はS字カーブを描いている首の骨が、真っ直ぐになっている状態をストレートネックといいます。
こちらはスマホ首とも呼ばれるもので、スマホの使用率が高い昨今、子どもにもよく見られます。
ストレートネックの場合、頭が常に前かがみの状態になっているため、下顎は重力で前下方に引っ張られています。
下顎が引っ張られている影響で、上顎との噛み合わせがずれる傾向があります。
具体的には、正中のズレや過蓋咬合といった不正咬合のリスクが高まります。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・小児の舌癖は、歯が傾き、出っ歯になったり、舌が後方に下がり、受け口なったりするおそれがある
・舌癖は細菌感染などのリスクも上昇させる場合がある
・唇を噛む癖も、出っ歯や受け口のリスクが高くなる悪い癖
・爪を噛む癖がある場合、前歯が前方に引かれる時間が長くなり、出っ歯になりやすい
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
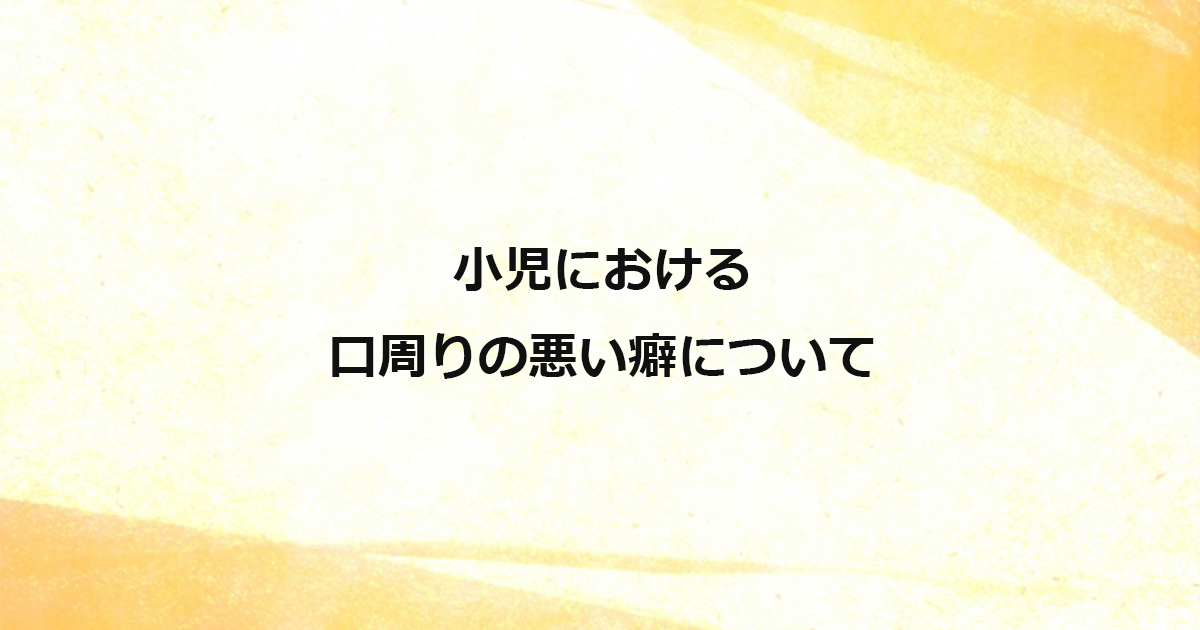

患者様のことを最優先に考えた、オーダーメイドの治療プログラムで対応させて頂きます。